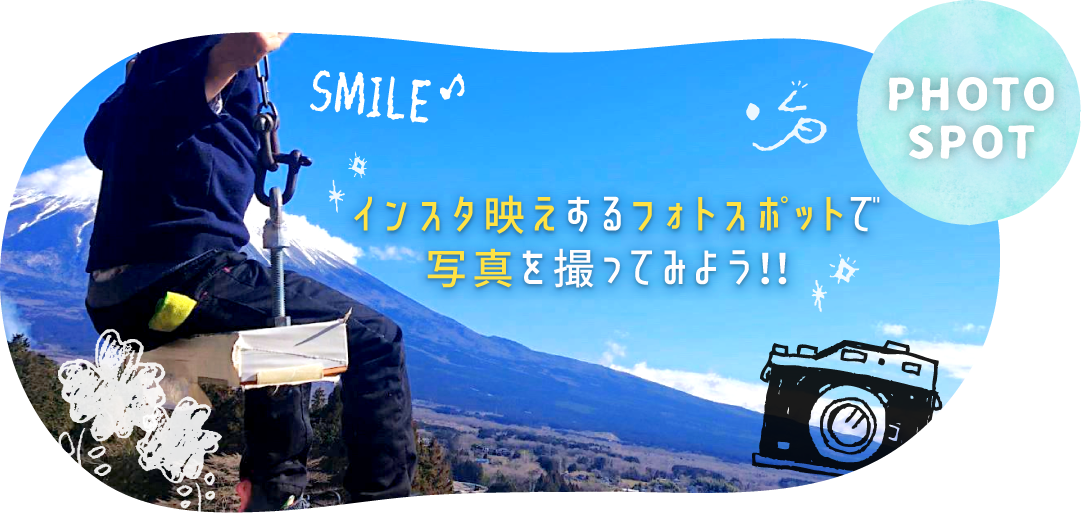まかいの牧場を楽しもう Enjoy the Farm!
Introduction場内紹介
Informationお知らせ
Pickup News
-

お知らせ
GW混雑のお詫び
いつもまかいの牧場をご利用頂き、誠にありがとうございます。 GW(4/27~5/6)は当施設で、十分な駐車台数が確保で...
-

イベント
GWのイベントスケジュール(4/27~5/6)
2024年4/26~5/6日のイベントのタイムスケジュールです。印刷にはイベントスケジュール【こちら】(pdf)をご利用くだ...
-

お知らせ
めぇ~めぇ~権 募集結果のおしらせ
まかいの牧場では、2024年3月末まで「めぇ~めぇ~権」の販売をさせていただきました。 43件の多数の素晴らしいお名前...
-

お知らせ
ソフトクリーム価格改定のお知らせ
いつもまかいの牧場をご利用頂き、誠にありがとうございます。 この度は、昨今の原材料の高騰などにより...
-

お知らせ
羊の毛刈り入社式開催
まかいの牧場では、新入社員を迎えるにあたり、一風変わった入社式を開催いたします。 羊の毛刈りを迎え...
-

イベント
イベントスケジュール(4/1~4/26)
2024年4月1日~4月26日のイベントのタイムスケジュールです。印刷にはイベントスケジュール【こちら】(pdf)をご利用く...
-

お知らせ
GW短期バイト募集のお知らせ
まかいの牧場では、GWの短期アルバイトを募集しております!! 興味がある方はご連絡下さい!! ...
-

お知らせ
【農場レストラン】お花見弁当販売のお知らせ
まかいの牧場、農場レストランでいただきますでは、3/30(土)・31(日)の2日間限定の13品のスペシャル弁当『お花見弁当』...
-

お知らせ
めぇ~めぇ~権はじめました!
まかいの牧場では、1月13日からヤギの赤ちゃんが生まれ、とても小さく可愛らしい姿を見る事ができます。 昨年に引き続き、...